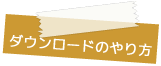桜の名所としてのほうがメジャーな印象がある仁和寺さんですが、紅葉の季節もすばらしいです。穴場といえる場所かと思います。
御殿の庭園はさらに素敵です。
仁和寺五重塔とカエデ。
参拝者の影も長い夕暮れの仁和寺五重塔。
西の山に日が沈んでいきます。
西日に照らされて赤い五重塔。
山から見る秋の五重塔。背の高い木々にカエデは隠されてしまい、赤い色は見えません。
山門のまわりはいくぶんか秋の景色になっていました。
京都の観光地や神社・寺院・世界遺産・史跡・風景をフリー写真素材としてお使いいただけます。京都の紹介にどんどんお役立てください。

桜の名所としてのほうがメジャーな印象がある仁和寺さんですが、紅葉の季節もすばらしいです。穴場といえる場所かと思います。
御殿の庭園はさらに素敵です。
仁和寺五重塔とカエデ。
参拝者の影も長い夕暮れの仁和寺五重塔。
西の山に日が沈んでいきます。
西日に照らされて赤い五重塔。
山から見る秋の五重塔。背の高い木々にカエデは隠されてしまい、赤い色は見えません。
山門のまわりはいくぶんか秋の景色になっていました。
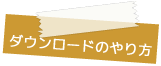
美しい秋の金閣寺さんの写真です。
金閣寺境内のあちこちに見事な紅葉の景色があります。
手前にカエデの木が配してあり、枝振りもほどよくデザインされています。

まわりはツアーの団体さんと修学旅行の団体さんと海外からの観光客でごったがえしています。

陸舟の松。元は足利義満の盆栽の松だったとか。
※ 銀閣寺・金閣寺の写真はテレビや書籍には使えないようです。
個人的な目的にのみお使いください。
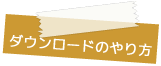
Kiyomizu-dera
東山の清水寺さんの紅葉の写真です。京都を代表する紅葉の名所です。
夕日に照らされる晩秋の清水寺。
定番中の定番のアングルです。順番待ちして譲り合わないと撮れません。
暮れていく空に三重塔。
カエデ越しに見上げる三重塔。
いまとなっては珍しい修復中にしか見られない紅葉の景色。
奥の院からの景色。
定番の景色。修復工事で見られない期間もとても長かったです。
清水の舞台から。強い朝日を浴びて真っ赤っか!
赤い山に泰産寺の子安の塔が建ちます。
強い日差しにカエデの赤がさらに発光してまぶしいほど。さすがは清水寺。
桜もたくさんありますし、常緑樹もけっこう多いですが、それでも赤いです。
お向かいの山から見る清水寺境内全景。
舞台のうえは人がいっぱい。今日は拝観はやめとこうと思いました。
次は夜間拝観の清水寺写真。
夜5時半にライトアップが始まります。LEDだからか徐々に明るくなっていくように思います。
拝観の入り口、仁王門。
仁王門を抜けて石段をまた上がり、三重塔へ。
清水寺三重塔。
清水寺三重塔。
舞台から正面を見て。向いの山には子安の塔。
舞台から左手を見ると奥の院が見えます。
右下には音羽の滝。
左手にはレーザー光の発射装置。
奥の院をよく見るとこぼれ落ちんばかりの人の数。
あそこから舞台を見るのがもっとも有名な景色となっています。
よく見るとみなさん手を伸ばして助けを求めているよう。後列から写真を撮るにはそれしかないのです。
そしてその定番の景色、奥の院から見る清水の舞台。
ワイドに。
ここからの写真を撮るためには延々と続く行列に並ぶ必要があります。
進んでいるか進んでいないのかわからないような行列です。
奥の院までたどり着いてから最前列に進むまでにも長い時間がかかります。
がんばりました...。
(奥の院をスルーしてもよければ、お堂の裏側を回ってスムーズに進めます。)
奥の院を過ぎてしまえばあとは比較的ゆったりと景色を見ることができます。
三重塔がきれいです。
子安の塔もまたちらっと見えます。
音羽の滝へと下りる石段から舞台を見て。
カエデの染まり具合はまちまちですが、ライトできれいに見えます。
清水さんは長年に渡ってライトアップをされているので、ライトの配置や光の当て方も洗練されているように思います。
順路の終わり際、舌切り茶屋あたりから見上げる三重塔。
池のリフレクションもきれい。
この日は風があったので、鏡のようではありませんでした。
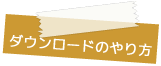
奥嵯峨の浄土宗のお寺、化野念仏寺さんの写真です。
平安時代から葬送地として知られる場所。お盆の千灯供養が有名です。
もう閉門時間の過ぎた夕方の山門。
紅葉の季節。遠目に見る化野念仏寺。
紅葉の季節。
カエデが見事に染まりました。
石仏群のグレーゾーンのまわりを真っ赤なカエデが囲みます。
石仏群は1903年にこのあたりに点在していた石仏を集めて整理したものだということです。
敷き紅葉のなかの石仏。